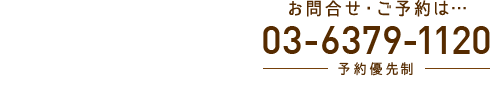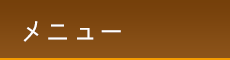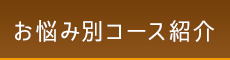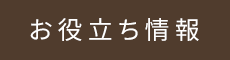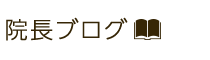「デスクワークで姿勢が悪いから肩こりになる」
「運動不足が原因かも」
こうした説明はよく聞かれますが、実はそれだけではありません。

当院に来られる多くの方が、正しい姿勢を意識しても、マッサージを受けても、なかなか肩こりが根本から改善されないとおっしゃいます。
実はその原因の一つに 「内臓疲労」、特に肝臓の疲れ が関係していることをご存知ですか?
この記事では、
-
なぜ肝臓の疲れが姿勢に影響するのか
-
姿勢の悪化がどうして肩こりにつながるのか
-
そして整体的にどう対処すればよいのか
この3つを、専門的に、しかしわかりやすくお伝えします。
1. 肩こりと姿勢の深い関係

まず、肩こりと姿勢の関係について簡単に整理しておきましょう。
現代人の多くは、スマホ・パソコンの長時間使用により「猫背姿勢」「頭部前方位」と呼ばれる姿勢をとりがちです。これにより、
-
首や肩周りの筋肉が常に緊張
-
血流が悪化
-
筋肉の酸素不足と老廃物の蓄積
といった連鎖が起こり、肩こりにつながります。
しかし、なぜ人は猫背になってしまうのでしょうか?
ただの「筋力不足」や「癖」では説明しきれないケースも多くあります。
そこで注目したいのが 「内臓の位置や状態」 です。
2. 姿勢と内臓の意外なつながり

私たちの体は、骨と筋肉で支えられていますが、その筋肉や骨格の働きを微妙に変えるのが「内臓の状態」です。
内臓の疲労があると、体は無意識のうちにその部位を「守ろう」とします。
つまり、 内臓をかばうような姿勢 を無意識にとるようになるのです。
特に肝臓は、体の右側、肋骨の下あたりに位置しており、疲労すると以下のような姿勢の変化が起こります:
-
体が右に傾きやすくなる
-
骨盤が後傾し、猫背気味になる
-
横隔膜の動きが制限され呼吸が浅くなる
このようにして姿勢が崩れると、当然、首や肩に不自然な力がかかり、肩こりの原因となるのです。
3. なぜ肝臓が疲れるのか?
肝臓は「沈黙の臓器」と言われ、症状が出にくい反面、疲労は溜まりやすい臓器です。現代人に多い肝臓疲労の原因は次の通り:
-
食べ過ぎ・飲み過ぎ(特に脂肪・糖質・アルコール)
-
睡眠不足・過労
-
薬やサプリメントの過剰摂取
-
ストレスによる自律神経の乱れ
これらによって肝臓が疲れると、代謝が落ち、血液の浄化や栄養の処理能力が低下します。その結果、全身の筋肉が硬くなりやすく、回復力も低下します。
4. Liberta整体院のアプローチ:肝臓疲労にどう対応するか?

当院では、単に肩をもんだり、姿勢を矯正したりするだけではありません。
◆ アプローチ1:内臓マニュピレーション
内臓(特に肝臓)へのやさしい手技によって、動きを改善し、負担を軽減します。肝臓の位置が整うことで、横隔膜や周囲の筋膜の緊張がとれ、自然と姿勢が整いやすくなります。
◆ アプローチ2:姿勢と歩行の調整
肝臓が回復しても、姿勢の癖が残っていれば再発しやすいため、骨盤や背骨のアライメントを調整し、正しい姿勢を体に覚えさせます。また、歩行パターンにも着目し、体の重心を自然な位置に戻します。
◆ アプローチ3:生活習慣アドバイス
以下のような肝臓に優しい生活指導も合わせて行っています:
-
夜11時までに就寝(肝臓の修復は夜に行われます)
-
アルコールや甘いものを控える
-
深い呼吸で横隔膜をよく動かす
-
ストレスケアやリラックスの時間を取る
5. 「肝臓から整える」ことで得られる効果
肝臓の疲れを取り、姿勢を整えることで、肩こりだけでなく、以下のような副次的効果も期待できます:
-
呼吸が深くなり疲れにくくなる
-
頭痛や目の疲れが軽減
-
朝の目覚めがスッキリ
-
集中力の向上
-
内臓機能の向上による体全体の軽さ
これは、一時的なマッサージでは得られない「根本的な変化」です。
まとめ:肩こりを本当に治したいなら「内臓」も見るべき
肩こりの原因は単なる姿勢の悪さや筋肉の硬さだけではありません。
その奥にある「肝臓疲労」を見逃してはいけません。
整体は骨格だけでなく、内臓や神経、血流、呼吸など全身のバランスを整える療法です。
長年の肩こりや疲れに悩んでいる方こそ、 「肝臓から姿勢を見直す整体」 を一度体験してみてください。
ご自身の身体と向き合い、内側から整えていくことが、根本改善への第一歩となるはずです。
気になる方はHPよりお気軽にお問い合わせください!